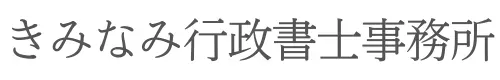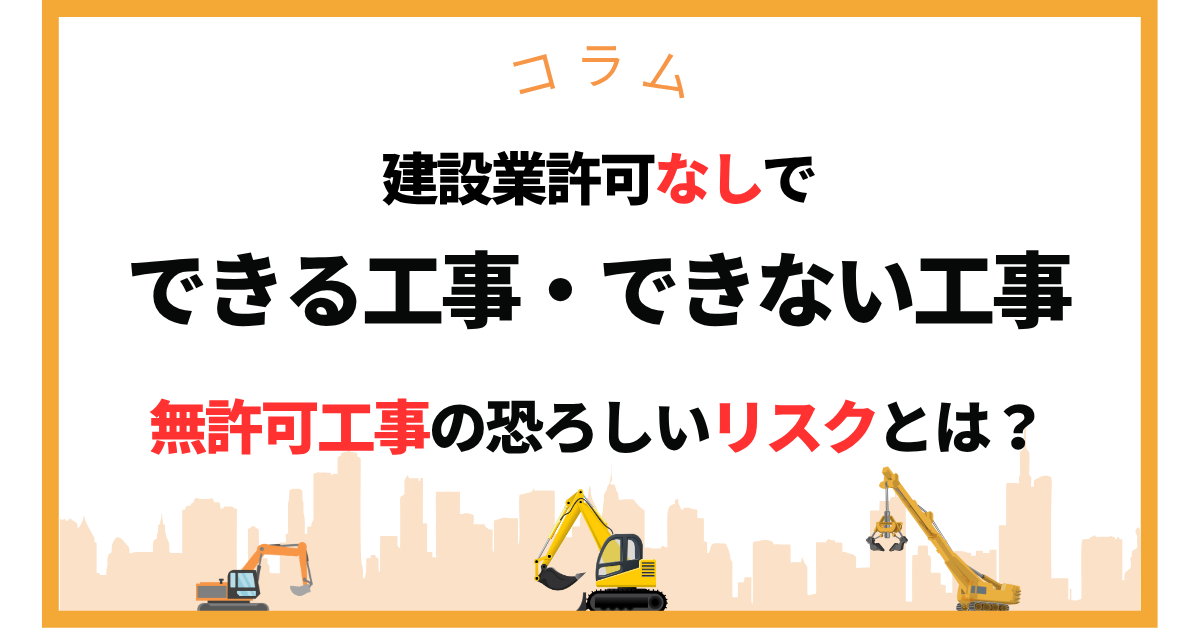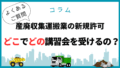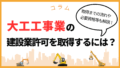姫路市のきみなみ行政書士事務所です。
「うちは小さい工事しかしないから大丈夫」「個人事業主だし、許可なんていらないでしょ?」
もし建設業の事業者さんがそう思っているなら、とても危険です。
建設業を営む上で、実は「建設業許可」が必要なケースとそうでないケースがあります。この境界線を曖昧にしていると、知らず知らずのうちに「無許可営業」と見なされ、厳しい罰則が科せられるだけでなく、事業の信用を失い、廃業に追い込まれる可能性すらあります。
「自分は大丈夫」と思っている方も、ぜひ一度、ご自身の事業が適正か確認してみてください。
「許可なしでできる工事」と「許可が必要な工事」の境界線とは?
まず、建設業許可が不要な「軽微な建設工事」から確認しましょう。
【許可が不要な「軽微な建設工事」とは?】
建設業法では、以下のいずれかに該当する工事を「軽微な建設工事」と定め、建設業許可がなくても請け負うことができます。
- 建築一式工事の場合:
- 1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
- または、延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の場合(電気工事、内装工事、管工事など):
- 1件の請負代金の額が500万円未満の工事
「500万円未満」というのは、消費税込みの金額であることに注意が必要です。うっかり消費税を抜きで計算して、軽微な工事の枠を超えてしまうケースもあります。
【許可が必要な「軽微な建設工事」を超える工事】
上記「軽微な建設工事」の基準を超える工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要となります。
- 例えば、請負代金が600万円の電気工事を請け負う場合
- 請負代金が2,000万円の一戸建て新築工事を請け負う場合
これらの工事を行うためには、事前に適切な種類の建設業許可を取得している必要があるのです。
なぜ「軽微な工事」の基準があるのか?
建設業許可は、発注者保護と建設工事の適正な施工を確保するために設けられています。ある程度の規模以上の工事は、施工能力や経営状態がしっかりしている業者に行ってもらう必要がある、という考え方に基づいているためです。
無許可工事がバレるとどうなる?
「バレなきゃ大丈夫」と安易に考えていると、取り返しのつかない事態を招きかねません。無許可工事が発覚した場合のリスクは非常に大きいです。
リスク1:厳しい罰則(懲役・罰金)
建設業法では、無許可工事に対して罰則が定められています。
- 建設業許可を受けずに建設業を営んだ場合
- 3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金
事業主個人だけでなく、法人にも罰金が科せられるケースもあります。
リスク2:請負契約の無効・請負代金の回収不能
無許可工事を隠して締結された請負契約は、有効性が問われる可能性があります。
- 工事代金が支払われない!
- 発注者側が「許可がない業者との契約は無効だ」と主張した場合、工事をしても代金が回収できなくなるリスクがあります。
- 訴訟問題に発展!
- トラブルになった際、無許可であることが発覚すれば、法的に非常に不利な立場に置かれます。
リスク3:事業継続が困難に!信用失墜と廃業の危機
無許可工事が行政庁に知られると、以下のような事態に陥る可能性があります。
- 行政指導・営業停止処分:
- 工事の受注が一切できなくなり、事業がストップします。
- 社会的な信用失墜:
- 「違法な業者」というレッテルが貼られ、金融機関からの融資が受けられなくなったり、元請けからの取引停止、新規の顧客獲得が絶望的になります。
- 入札参加資格の剥奪:
- 公共工事への参入を考えていた場合、完全に道が閉ざされます。
- 社員・従業員の離職:
- 会社の先行き不安から、優秀な人材が離れていく可能性があります。
これらのリスクは、単なる罰金で済まない、事業そのものを揺るがす重大な問題です。一度失った信用を取り戻すのは至難の業です。
「軽微な工事だけ」と思っていても要注意!知らずにラインを超えるケース
知らず知らずのうちに「軽微な工事」のラインを超えてしまうケースもあります。
- 請負契約が分割されているケース:
- 例えば、請負代金が800万円の土木工事を、意図的に400万円ずつ2つに分けて契約した場合でも、実質的に一体の工事とみなされ、無許可工事と判断されます。
- 追加工事で金額が膨らんだケース:
- 当初は500万円未満の契約だったが、追加工事が発生し、結果的に総額が500万円を超えてしまった場合。この場合も、許可が必要になります。
- 元請けからの指示で請負金額が変動したケース:
- 元請けとの関係で、工事内容や金額が途中で変更になり、知らない間に許可のラインを超えてしまうこともあります。
これらのケースは、意図的でなくても「無許可工事」と見なされる可能性があります。
特に近年の急激な物価上昇により、数年前だったら500万円を超えなかったのに…!という事業者様が最近本当に多いです。請負金額には常に注意を払う必要があります。
建設業許可取得は、あなたの事業を守る「最高の防御」
ここまで読んで、「もしかしたらうちも危ないかも…」と感じた方もいるかもしれません。
建設業許可は、ただの面倒な手続き、ではありません。あなたの事業を法律で守り、より大きなビジネスチャンスを掴むための「許可証」なのです。
また、許可を取得することで、以下のようなメリットがあります。
- 法的リスクからの解放: 無許可工事の心配なく、安心して事業に専念できます。
- 事業拡大のチャンス: 大規模な工事や公共工事への参入が可能になります。
- 社会的信用の向上: 許可業者としての信頼性が増し、元請けや金融機関からの評価も高まります。
- 優秀な人材の確保: 安定した事業基盤は、優秀な人材を惹きつけます。
まとめ:今すぐチェック!あなたの事業は大丈夫?
「軽微な建設工事」の基準を少しでも超える工事を請け負う場合、建設業許可は必須です。
もし、ご自身の事業が許可の対象になるのか不安な方、許可取得の準備を進めたいけれど何から手をつければ良いか分からない方は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。
当事務所では、建設業許可に関する無料相談を受け付けております。事業者様の状況をお伺いし、最適なアドバイスをさせていただきます。