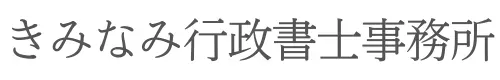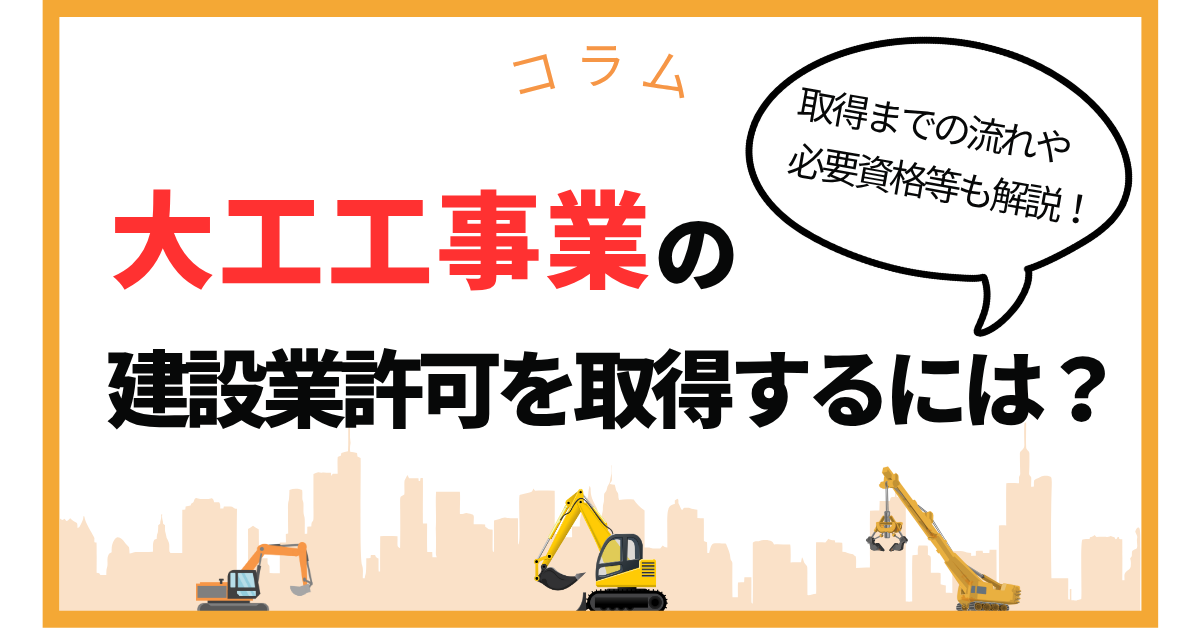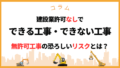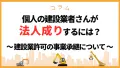こんにちは!姫路市のきみなみ行政書士事務所です。
「もっと大きな仕事を受注したい」「元請けから許可があるか聞かれた」
そのような建設業の事業者様にとって、建設業許可の取得は避けて通れない道です。
でも、「許可って難しそう…」「何から手をつけていいか分からない」と感じていませんか?
そこで、今回は大工工事業の建設業許可を取得するための要件や資格等をわかりやすくご説明いたします。
この記事を読めば、あなたが今すぐ許可取得に向けて何から始めるべきか、明確に理解できるはずです。ぜひ最後までご覧ください!
大工工事業ってどんなもの?
まず、大工工事業の建設業許可が具体的に何を指すのかを確認しましょう。
「大工工事業」が対象とする工事とは?
建設業許可には29の業種がありますが、「大工工事業」は主に以下のような工事を指します。
✅木材の加工又は取付けにより工作物を築造する工事
✅工作物に木製設備を取り付ける工事
具体例としては
- 大工工事
- 型枠工事
- 造作工事
などがあります。
壁紙の張り替えや内装仕上げは「内装仕上工事」、ガラスやサッシの取り付けは「ガラス工事」ドアの取り付けは「建具工事」など、別の許可業種になる場合もあります。リフォーム中心の事業者様は、税込み500万円を超えそうな業種の許可を中心に取得すると良いと思います。複数の業種を請け負う場合は、それぞれの許可取得が必要になることも覚えておきましょう。
大工工事業許可取得の6つの要件
建設業許可を取得するためには、大きく分けて6つの要件をすべて満たす必要があります。どれか一つでも欠けると許可は下りません。
1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任の技術者がいること
3.誠実性があること
4.財産的基礎・金銭的信用があること
5.欠格要件等に該当しないこと
6.適切な社会保険に加入していること
要件1:経営業務の管理責任者がいること
法人の役員や個人事業主として、適切な建設業の経営経験がある人物がいることです。
具体的には
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理経験(個人事業主や役員経験など)がある
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位として6年以上の経営業務の管理経験がある
などがあります。
要件2:専任技術者がいること
許可を受けようとする建設業(この場合は大工工事業)に関する専門知識や技術を持つ技術者がいることです。
こちらに関する資格学歴などは後述いたします。
要件3:誠実性があること
申請者(法人であれば法人、個人であれば個人事業主)やその役員等が、不正行為や不誠実な行為を行うおそれがないことです。
要件4:財産的基礎・金銭的信用があること
事業を継続するだけの財産があることです。
- 一般建設業の場合
- 自己資本が500万円以上あること
- または、500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)
- 特定建設業の場合
- 資本金が2,000万円以上で、かつ自己資本が4,000万円以上あることなど、より厳しい基準があります。
要件5:欠格要件に該当しないこと
申請者や役員等が、建設業許可が与えられない特定の事由に該当しないことです。
要件6:適切な社会保険に加入していること
適切な健康保険・年金・雇用保険に加入していますか?それぞれの事業所によって適切な社会保険が違います。
建設業許可の要件は、どの建設業種も必要となる要件の詳細はほぼ一緒です。
しかし、専任の技術者は取得しようとしている建設業種ごとに必要な資格や学歴が違いますので、ご注意ください。
一般建設業で大工工事業の専任の技術者になれる資格・学歴など
一般建設業で大工工事業の建設業許可を取得するには、下記の①~③のいずれかに該当する人を専任の技術者として、各営業所に常勤で置かなければなりません。
①指定の国家資格等を有している人
一般建設業で大工工事業の専任の技術者になれる資格は以下の通りです。
②指定学科を卒業、かつ一定の実務経験を有している人
大工工事業の指定学科は「建築学または都市工学」となり、卒業後に一定の年数の大工工事の実務経験を有していれば専任の技術者になることができます。
③10年の実務経験を有している人
大工工事に関して10年以上の実務経験を積むと、一般建設業の専任の技術者として認められます。
実務経験は客観的資料によって経験を証明します。
特定建設業で大工工事業の専任の技術者になれる資格など
特定建設業で大工工事業の建設業許可を取得するには、①~③に該当する人を専任の技術者として、各営業所に常勤で置かなければなりません。
①指定の国家資格等を有している人
特定建設業で内装仕上工事業の専任の技術者になれる資格は以下の通りです。
②一般建設業の専任技術者の要件を満たしたうえで、大工工事で4,500万円以上の元請工事に関し2年以上の指導監督的経験を有している人
指導監督的経験とは、工事現場主任者・工事現場監督・主任技術者・工事主任・現場代理人・設計監理者・施工監督等として、工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことを指します。
③国土交通大臣が①、②と同等の能力を持っていると認めた人
許可取得までの流れと、スムーズに進めるためのポイント
建設業許可取得までの一般的な流れは以下の通りです。
- 要件の確認・書類収集の準備
- まずは、要件を満たしているか確認します。特に「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件は厳しいため、事前に確認が必須です。
- 必要となる書類のリストアップと、収集計画を立てます。
- 必要書類の収集・作成
- 各種証明書の取得、実務経験を証明する資料(請求書など)の収集、財務諸表の作成など。
- 申請書類の作成
- 申請書や添付書類を作成します。
- 行政庁への申請
- 管轄の行政庁に申請します。
- 審査
- 申請から審査完了まで、知事許可で約2ヶ月、大臣許可で約3ヶ月~4ヶ月が目安です。(混雑状況により変動します)
- 許可通知
- 審査に通れば、許可通知書が届き、晴れて許可取得となります!
スムーズに許可取得するためのポイント
- 早めの準備と計画性: 特に実務経験の証明書類などは、過去に遡って集めるのが大変な場合があります。余裕をもって準備に取り掛かりましょう。
- 専門家への相談:
- 「どの要件を満たせるか不安」「書類作成が複雑で自信がない」という場合は、建設業許可に詳しい行政書士に相談するのが最も確実で効率的です。
- 行政書士は、要件診断から書類収集のアドバイス、書類作成、申請代行までトータルでサポートします。
- 複雑な申請を自力で行うよりも、結果的に時間と労力の節約になるでしょう。
まとめ
大工工事業の建設業許可取得は、あなたの事業を拡大していくための重要なステップです。
「許可を取りたいけれど、何から手をつけていいか分からない」、「自分の経験や資格で許可が取れるのか知りたい」
そんな疑問やお悩みがあれば、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。あなたの事業が飛躍するためのサポートをさせていただきます。