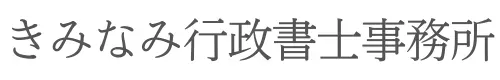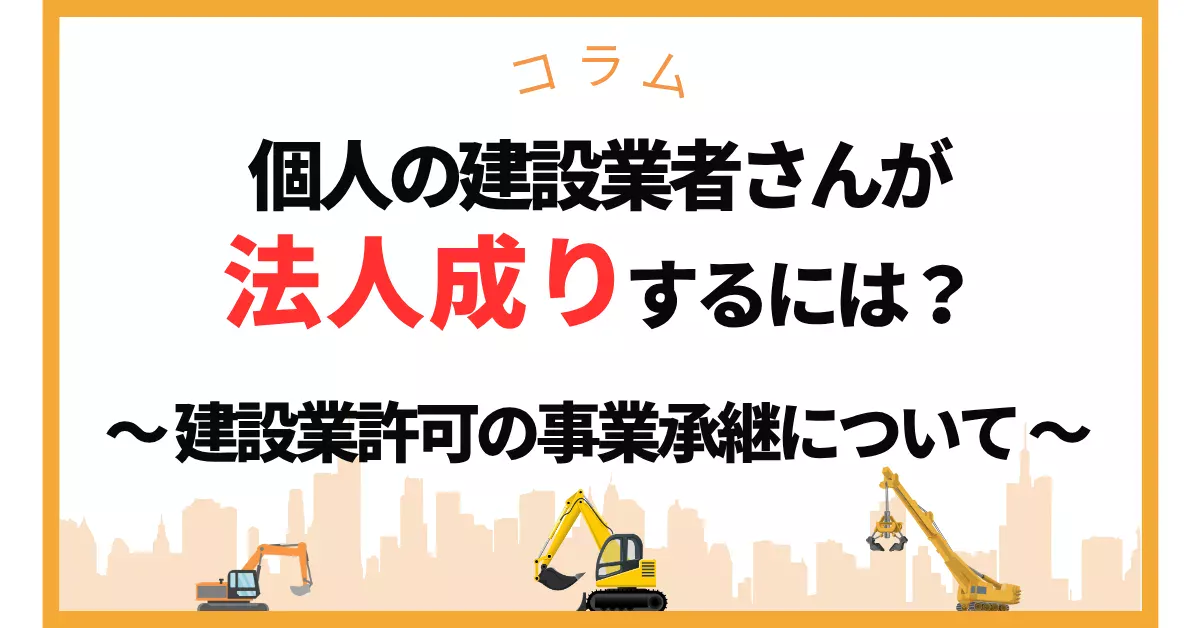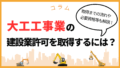個人事業として建設業許可を取っていらっしゃる建設業者さんが法人化を考えるとき、建設業許可は引き継げるのかどうかが大きなポイントになることがあります。
個人事業主として建設業許可を持っているからといって、新設した法人で税込500万円以上の工事を請け負ってしまいますと、建設業法違反となってしまいます。
しかし、新設した法人で新規で建設業許可を取るとしたら、申請から許可日までの審査期間(最短でも1~2ヶ月程度)に、建設業許可のない空白期間が出来てしまい、事業が滞ってしまうこともあります。
せっかく事業を拡大するために法人成りをしたのに、一時的に許可を失い、事業を抑えなければならなくなるのは困る…この難しさを解消するのが、令和2年から施行された事業承継認可制度です。
今回は1人親方の法人化(法人成り)に特化して、建設業許可の事業承継認可についてご説明いたします。
建設業許可の事業承継認可とは
建設業許可の事業承継認可制度とは、建設業許可を持っている事業者さんに合併、分割、法人化等の事由が生じた場合に、建設業者としての地位を空白期間なく承継者等に承継させる制度です。
1人親方の法人化に関して、建設業事業承継のメリット、デメリットは以下のとおりです。
メリット
- 空白期間を作ることなく建設業許可を引き継げる
- 個人事業主時代の許可番号が変わることがなく使用できる
- 新規の申請とは違い、行政への申請手数料(9万円)がかからないため、新規申請よりも安く許可を取れる※
- 認可が下りた日から5年が許可の有効期限になるため、更新は5年後で良い
※行政書士による報酬は新規申請よりも事業承継申請の方が高くなることが多いようですので、代理で申請した場合は必ずしも安く許可を取れるとは言いかねます。
デメリット
- 手続きが新規申請よりも煩雑になることが多い
- 社会保険の移行の問題等があり、制約が多い
- 手続き前に窓口に相談※、認可後にも必要書類を提出しなければならず、会社設立後で忙しい中、申請窓口に何度も行かなければならない
※筆者の事務所のある地域の建設業課(姫路土木事務所)では現在のところ相談は必須です。
以上のようにメリット・デメリットがあり、特に自社で許可申請を行っている事業者さんは、事業承継手続きが煩雑すぎるためか、仕方なく新規申請を選ぶ、という事業者さんも多いとのことです。
法人成りで建設業許可を事業承継するための要件
建設業の事業承継を行うために、満たさなければならない要件があります。
- 事業承継認可は承継の効力発生日よりも前に受けること
- 承継元の建設業許可の全部を承継すること
- 建設業許可の取得要件を満たしていること
以下で1つずつ解説しましょう。
事業承継認可は効力発生日よりも前に受けること
事業承継に係る申請を行う場合は、被承継人(個人事業主)と承継人(新設法人)との間で事業譲渡契約が行われている必要があります。
ただし、事業承継の事実(効力)の発生後には認可を受けることが出来ないため、事実の発生前に認可を受けなくてはなりません。
このため、兵庫県では、効力発生日の45日前(土日祝を除く)には認可申請書を提出してなければなりません。
申請書の提出時期は各自治体によって違いがありますので、申請先の自治体の手引きを確認してください。
承継元の建設業許可の全部を承継すること
個人事業として取得していた建設業許可のうち、一部の許可だけを新設法人に引き継がせるということはできません。必ず、承継先は、承継元の建設業許可を全て承継することとなります。
一部の建設業許可のみを承継したい場合は、認可申請の前に一部を廃業してから残りの全てを承継することとなります。
建設業許可の取得要件を満たしていること
事業承継先となる新設法人でも、新規の許可と同じように建設業許可の取得要件を満たしている必要があります。
建設業許可の取得要件は以下のとおりです。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任の技術者がいること
- 誠実性があること
- 財産的基礎・金銭的信用があること
- 欠格要件等に該当しないこと
- 適切な社会保険に加入していること
ただし、6に関しては要注意です。
社会保険に関しては、新法人の設立後、慌てて加入してはなりません。
認可日以前に社会保険の加入をしてしまいますと、個人としての常勤性が失われたと認識されてしまい、承継元の許可が失われてしまうからです。
このような予期せぬ許可の喪失を防ぐためにも、そろそろ法人化を…と考えていらっしゃる個人事業主様は設立前に申請窓口に相談したり、建設業許可に詳しい行政書士にご相談ください。
事業承継の認可日までは個人事業として常勤、認可日からは新設法人で常勤、ということになるように、社会保険の手続きには細心の注意を払う必要があります。
法人成りの事業承継のポイント
上記で述べたように、特に社会保険の手続きに関して、しっかりとスケジュールを組んで行うことが非常に重要です。社労士さんと契約されている事業者さんは、設立前に社労士さんとの打ち合わせが必要となるでしょう。また、加入している健康保険によっては、健康保険の窓口に事前に相談する必要がありますので、ご確認ください。
他のポイントとしては、
- 申請窓口との打ち合わせ
- 事業譲渡契約書や議事録など、新規申請の際には必要なかった書類の準備
- 認可後の社会保険関連の書類の提出
などがあります。
法人化をお考えの事業者さんは、会社設立前からしっかり打合せをし、計画立てて建設業の事業承継を行うのが、成功の要です。
まとめ
法人成りに伴う建設業許可の事業承継に関して、ご理解いただけましたでしょうか?
まだ事業承継の件数が多くないこともあり、1例1例、この場合はどうすれば良いですか?と窓口とやり取りしなくてはならないことが多いです。
また、社会保険の移行など、新会社の設立や現場でのお仕事と、忙しい事業者さんにはとにかく面倒な手続きが多い申請です。
建設業に詳しい行政書士に申請を依頼すれば、申請書の作成・提出はもちろん、窓口との打ち合わせや、細やかなスケジューリングも行政書士任せにできます。
兵庫県姫路市、また、近隣の自治体での建設業の許可申請は、ぜひ1度、きみなみ行政書士事務所にご相談ください。