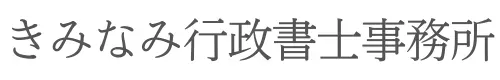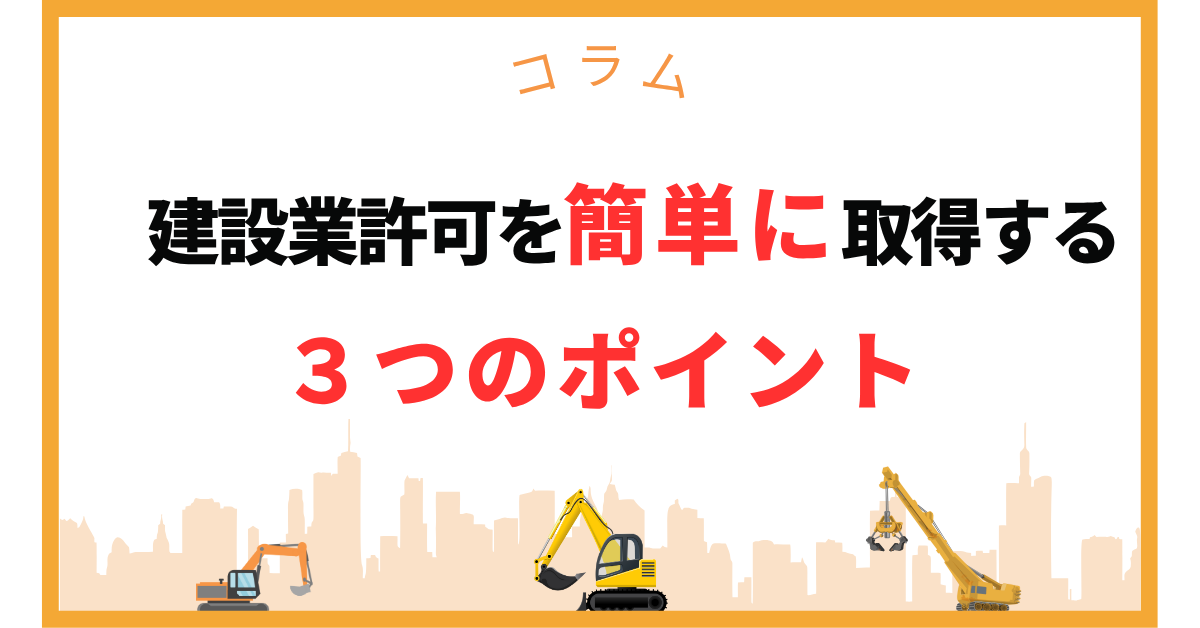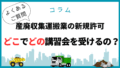建設業許可を取りたいと思ったときに、用意すべき書類が足りずに許可取得を断念する方が多くいらっしゃいます。
行政書士としても、お客様が建設業許可を取得できるように、このような書類を持ってないかと色々提示して、努力はさせていただくのですが、やはり許可を取りたいと思った段階によっては書類の未保存や記載方法の間違いでどうにもならないパターンが一定数ございます。
今回は、今後建設業許可を取りたいと思っている方向けに、簡単に取得するための準備として大切なポイントを何点かご説明いたします。
請求書は取りたい建設業の種類まで記載する
建設業許可の申請の際、建設業を行った経験を示すために請求書の写しの提出が求められます。
兵庫県ですと、10年の実務経験を証明するために1年4枚程度、計40枚です。
経営業務の管理責任者としても5年分必要になることが多いため、請求書は必ずしっかりと保存しておいてください。
特に専任技術者を証明するための請求書の大切なポイントは、その工事の建設業の業種をしっかりと記載しておくことです。
申請先の行政庁は、その請求書を見て、しっかりとその建設業種を行っていたかを確認します。
現場名、工事内容が「工事一式」、金額、のみが書かれている請求書だけでは、建設業を行っていたとはわかるかもしれませんが、残念ながらその建設業種を行っていたとは証明することは難しいです。
その場合、別途詳細の記載されている見積書や契約書を提出するか、その工事の請求書を証明として使うことを断念することになります。
実務経験の証明に手間取らないようにするためには、請求書に建設業種の記載をお願いいたします。
個人の確定申告書には建設業と記載
1人親方が建設業の経営をしていたことの証明方法は確定申告書のみになります。
この確定申告書に記載すべきことが記載されていないと、例え1人親方として何年も建設業を行っていたとしても経営経験、実務経験が証明されない可能性がかなり高くなります。
職業の部分は大切なポイントです。
ここの記載がないと、常勤として建設業を行っていた、がほぼ証明できなくなります。
電気工事業等の業種名、事業主との記載でも問題なく通ることが多いですが、わかりやすいよう建設業と記載しておくのがベターです。
また、収入金額も必ず記載するようにしましょう。
収入金額がなく所得のみが記載された確定申告書は、建設業として売上がたっていたことの証明がどうしても難しくなってしまいます。
確定申告の作成が不安でしたら、税理士さんや、確定申告の期間が近付くと行われる税務署の確定申告相談会で、建設業の許可をいつか取得したい旨を話して作成をすると問題は起きづらいと思います。
建設業の経験がしっかりと許可取得に繋がるよう、正確に記載をお願いいたします。
確定申告書、法人税申告書は受信通知(メール詳細)まで残しておく
近年、確定申告の電子申告が多くなり、税務署の受領印を見ることが減りました。
電子申告を行うとe-Taxのメールボックスに受信通知(又はメール詳細)という、確定申告を受け付けましたよというお知らせが来ます。
この受信通知は、確定申告書を建設業許可申請の証明書類として提出した場合、ほぼ100%一緒に提出が必要になります。
10年の実務経験で建設業の取得を目指している場合、過去の受信通知(e-Taxのメールボックスは約5年保存)を保存していないと証明の難易度が高くなります。
受信通知は必ずパソコンに保存するか、紙で出しておき、しっかりと保存しておいてください。
余談ですが令和7年から税務署の受領印が廃止されました。
兵庫県のとある申請先にどう対応しているのかお伺いしたところ、とりあえず令和7年の分のみは受領印がなくても問題ないようです。
ただし、この先対応方法が変わる可能性はあるとのことでした。
まとめ
建設業許可を簡単に取得するポイントは、どのような書類を、どのように記載するかを理解し、しっかり保存しておくことです。
適切に保存された書類は建設業許可取得への近道となりますので、これから許可を取得しようと考えている方は、上記のポイントを頭の隅にいれておいてくださいね。